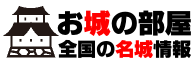石垣で有名なお城ランキング
第1位:金沢城(石川県金沢市)
天正8年(1580年)に佐久間盛政が築城。美しい石垣の数々は安土桃山時代から江戸初期にかけて石工集団「穴太衆(あのうたいしゅう)」が積み上げたものになります。
石垣には至るところに刻印あり、作業分担が分かるようにしたものと言われています。
 見どころは尾坂門石垣で大手門にあり、慶長時代に詰まれたと言われ堂々とした巨石が見られます。
見どころは尾坂門石垣で大手門にあり、慶長時代に詰まれたと言われ堂々とした巨石が見られます。また、丑寅櫓の石垣も見ごたえがあり、文禄時代に詰まれた石垣の中では、金沢城が現存する最古の石垣になります。
NHK番組「ブラタモリ」2015年5月2日放送で金沢城の石垣が紹介され、その美しさは歴史遺産より芸術生が高いことも指摘。
石垣だけでなく三十間長屋などの建造物もあり、一日かけてゆっくりと歴訪ができます。
35
第2位:大阪城(大阪府)
天正11年(1583年)に豊臣秀吉が築城。その後、元和6年(1620年)江戸幕府が改修。高さ30mの石垣は日本最大となり、場内には14畳敷き以上の石が10個もあります。
 石垣の積み方は豊臣期と徳川期で異なり、前者では未完成の算木積みが活用されたが、その構造はしっかりしたものです。
石垣の積み方は豊臣期と徳川期で異なり、前者では未完成の算木積みが活用されたが、その構造はしっかりしたものです。後者では完成した算木積みで積まれています。
見どころは本丸石垣で、本丸の石垣に三重櫓11基と多門櫓が聳えます。
本丸正面に当たる南内堀は空堀ですが、隅部は算木積みで勾配の美しさは見ごたえがあります。
さらに天守台は本丸の中心部に配置され、大天守の前に小天守台が付いています。
その他にも大手口や千貫櫓など、大阪城は見どころがたくさんあります。
26
第3位:萩城(山口県萩市)
萩城は慶長9年(1604年)に毛利輝元が築城。かつては高さ14.5mの五重の天守が建てられていましたが、今では天守台の石垣と堀が残されています。
天守台は東西約20.0m、南北約14.5m。萩城の魅力はこの天守台の石垣です。
 一般に石垣は敵からの攻撃を防ぐために急勾配にしますが、この石垣は緩やかな勾配のため、美しい曲線になっています。
一般に石垣は敵からの攻撃を防ぐために急勾配にしますが、この石垣は緩やかな勾配のため、美しい曲線になっています。その姿が堀の水面に映る光景はさながら一幅の絵画のようです。
石材には近くの山から切り出した花こう岩を使っており、その白い色彩が見る人の心を癒してくれます。
天守台の脇には日本屈指の雁木(がんぎ:兵が一斉に天守台に上る石段)があります。
横に長く続いているその光景も圧巻です。さらに二の丸の東面には日本一の横矢邪(よこやひずみ:城全体を緩く屈曲させたもの)という石垣が残っています。
19
第4位:中城城(沖縄県中頭郡)
14~15世紀頃に城主は護佐丸が築城したのではないかと言われています。
この城は二つの井戸と八ヶ所の御嶽(うたき:沖縄に分布する聖地のこと)からなる総石垣の城です。
 2000年に世界文化遺産に登録。建築物はなく、現存するのはほとんどが石垣になります。
2000年に世界文化遺産に登録。建築物はなく、現存するのはほとんどが石垣になります。見所のひとつが「城壁」。琉球石灰岩を高く積み上げており、美しい曲線美が眺められます。
石積みには野面積(自然の岩や石をそのまま組み合わせる最古の石積み方法)と布積み(直方体に加工した石を一段ごとに、きれいに高さをそろえて積む方法)の技法が取り入れられ、遠くから眺めるとさながらアートのようです。
もうひとつ「城門」も必見です。曲線を描く城壁と虎口のアーチ式の門で琉球の城のなかでは最高峰と言われています。
15
第5位:伊賀上野城(三重県伊賀市)
天正13年(1585年)に筒井定次が築城。現存しているものに手当蔵・石垣・水堀などがあります。
この城の特徴は縄張り(築城のプラン)が未完成であること。従って本丸から二の丸や御殿には繋がっていません。
 見所は本丸西側の高さ約30mの石垣となり、日本第2位の高さを誇る。
見所は本丸西側の高さ約30mの石垣となり、日本第2位の高さを誇る。隅石には算木積(石の長辺と短辺を段ごとに交互に組み合わせ、角をそろえて積む技術)を採用、また横矢となる塁線の張り出しが2ヶ所出ているのも印象的です。
もうひとつの見所は天守台の石垣です。打込接(石の接続部を加工し、隙間を減らす技術)を採用、角は算木積で全体に整った美観を呈しています。
また、天守台の南には井戸のある付櫓台が、さらに北には石垣の裏込石が高く積まれています。
未完成ながら堂々とした風格のある石垣は城へのロマンを呼び覚ましてくれます。
28
第6位:甲府城(山梨県甲府市)
文禄2年(1593年)城主の浅野長政が築城。現存するのが、本丸や天守曲輪などの石垣や天守台や堀の一部になります。
この城は天守台をはじめ総石垣造になっています。その造りは戦略的な役目を担っていたため、小規模ながらとても堅固です。
 特徴的なのは直線的な石垣が多く、鉄門脇の天守曲輪の石垣は上に鋭く伸びています。また城内には反りのある石垣があり、これらは古い時代の積み方になります。
特徴的なのは直線的な石垣が多く、鉄門脇の天守曲輪の石垣は上に鋭く伸びています。また城内には反りのある石垣があり、これらは古い時代の積み方になります。さらに古体の天守台も見どころです。台形をした野面積みの石垣が残り、平面は四隅が鋭角になって整っておらず古い時期の天守台特有の構造を表しています。
その他、見どころの石垣に虎口の石垣や埋殺しの石垣があります。富士山を背景に眺める甲府城は古い城として日本一と言えます。
21
第7位:金山城(群馬県太田市)
文明元年(1469年)若松家純が築城。金山全域に計画されたこの城は本丸を中心に周囲には複数の曲輪が配置されています。
現存するのは、堀・土塁・石塁・櫓台などです。
 過去に上杉氏や武田氏の攻撃を受けながらも落城できなかったことから、難攻不落の城として知られています。
過去に上杉氏や武田氏の攻撃を受けながらも落城できなかったことから、難攻不落の城として知られています。金山城は石を多用した総石垣の山城です。見どころはやはり石垣。
本丸に向かう途中に復元された大手虎口に着くとその両側に石積み、正面に土塁石垣が見えます。
石垣がしゃくれて見える「アゴ止め意石」も見ごたえがあります。この石は水が溜まり、地盤がゆるい箇所を補強するために置かれたと言われています。
さらに「月ノ池」「日地ノ池」といった池も見どころです。古から度重なる復元を経て今尚、調査が進むロマンあふれる城、それが金山城なのです。
16
第8位:丸亀城(香川県丸亀市)
慶長2年(1597年)に讃岐国主・生駒親正が築城。その後、寛永20年(1643年)や万治元年(1658年)にも修復。
丸亀城と言えば「石垣の名城」とも呼ばれ、曲線美を描く数々の石垣。その積み方の技術を挙げてみます。
 石垣の構築技術の一つである「切り込みハギ」は石を削るなどしして加工したものを合わせ、精巧に隙間なく積む方法。丸亀城の石垣の多くはこの積み方です。
石垣の構築技術の一つである「切り込みハギ」は石を削るなどしして加工したものを合わせ、精巧に隙間なく積む方法。丸亀城の石垣の多くはこの積み方です。次に打ち込みハギでは石を割って加工したのを使い、合わせ口を精巧に隙間なく積む方法になります。
丸亀城の石垣で一番の見どころは三の丸で高さは約22m。この石垣の隅部の石垣は算木積みという積み方です。
長方形の石を使い、長い面と短い面を交互に組み合わせることでより強固な石垣が築け、美しい勾配の高い石垣が造られたわけです。
16
第9位:備中松山城(岡山県高梁市)
天和3年(1683年)に水谷勝宗が築城。現存は、天守・二重櫓・石垣などが残り、特徴は天然の岩盤の上に築かれた石垣とさらにその上に築かれた白壁。
 見どころとしては天守で標高430mの高さの本丸にあり、長辺が約14m、日本一高い場所にある天守として知られています。
見どころとしては天守で標高430mの高さの本丸にあり、長辺が約14m、日本一高い場所にある天守として知られています。さらに雛壇状の石垣も見ごたえがあり、三の丸の奥に石垣が階段状に重なり、立体的で迫力があります。
岩盤上の石垣は必見で大手門北側、切り立った岩盤の上に高い石垣が築かれており、敵からの攻撃を防ぐために造られたものです。
「天空の城」としても知られている備中松山城。
雲上に聳える天守は歴史を実感できる一幕です。時期的には9月下旬から4月上旬の早朝が最適と言われています。
15
第10位:岡城(大分県竹田市)
滝廉太郎作曲「荒城の月」のモデルとなったお城。別名、豊後竹田城でも知られており、13世紀の築城後には幾度も改修され、現存は主に石垣となります。
この城の特徴は川に挟まれた丘の上に総石垣の城郭をそのまま築いた点にあります。
 石垣は算木積みで打ち込みハギと切り込みハギにより加工した石で積まれており、本丸の角隅には大きな石が整然と積み上げられた姿は圧巻です。
石垣は算木積みで打ち込みハギと切り込みハギにより加工した石で積まれており、本丸の角隅には大きな石が整然と積み上げられた姿は圧巻です。空を仰ぎながら天守を思い描けば、まさに「昔の光 今何処」です。
見どころは大手門から近戸門付近まで、高石垣で壮大な石垣のラインがが続きます。
長く続く外溝には櫓などの防御所も築かれており、さらに連続する外桝形虎口を持つ下原門もおすすめです。
16